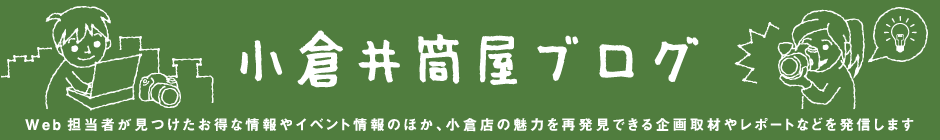

サステナブルピープル Vol.7
井筒屋グループは、企業の社会的責任を果たすべく、事業活動を通じてさまざまな社会課題の解決に貢献し、人々の豊かな未来と持続可能な(サステナブル)社会の実現を目指してまいります。本企画では、人と地域をつなぎ、豊かな未来を創造していくために、さまざまな業界のフロントランナーたちのお話を伺います。
![]()

1985年、遠賀郡遠賀町生まれ。九州栄養福祉大学食物栄養学部食物栄養学科卒業。卒業後は小倉リハビリテーション病院に入社。管理栄養士として働いていたが、病気になる前の段階で病気や怪我を防ぎたいと考え、福岡教育大学大学院へ進学。2012年、母校である九州栄養福祉大学で助手として入職後、2018年鹿児島大学大学院博士課程進学、2022年農学博士取得。2017年日本スポーツ栄養学会 公認スポーツ栄養士資格取得。![]()
今回ご登場いただくのは、大学でスポーツ栄養学や調理学などを学生に指導しながら、積極的に地域との連携事業に取り組んでいる室井由起子先生です。公認スポーツ栄養士としての活動に加え、廃棄されている「規格外トマト」を活用したメニュー開発や、サンタの衣装を着て地元の食を楽しむイベント「サンタウォークin到津の森公園」を開催し、学生たちと一緒に北九州の街を盛り上げようと、多彩な活動を展開しています。
![]()
・・・室井先生が食物栄養学を専攻した理由から教えてください。
母は食べ物に対して意識が高く、例えば添加物を避けるなど、口に入るものにこだわる人でした。専業主婦だったこともあり、私が幼い頃は毎日手作りのお菓子を作ってくれました。そうした家庭環境だったせいか、食べることには昔から興味がありました。これは余談ですが、友達と遊ぶようになって、初めてスナック菓子を食べたときは、すごく美味しくて衝撃を受けました(笑)。スポーツ栄養学の道に進んだ理由ですが、私は本学で栄養について学び、卒業後は管理栄養士としてリハビリテーションの専門病院で働いていました。そのとき主に取り組んでいたのは、“病気になった方を対象にした、回復させるリハビリ”でした。患者さんと接しているうちに「病気になる前に、食生活を通じた予防に取り組みたい」と考えるようになり、仕事を辞めて大学院へ進学し、そこでスポーツ栄養学を学びました。
![]()
・・・九州栄養福祉大学ではどのようなことを教えていらっしゃいますか?
地域連携についての授業や演習も多くなっていますが、私は公認スポーツ栄養士の資格所有者なので、スポーツ栄養学を専門とし、プロアスリートへの栄養指導も行っています。
例えば今、バレエ選手のサポートを行なっているのですが、バレエに本気で向き合う人は、若いうちから海外で挑戦する方が多く13〜16歳くらいの選手たちに、海外のスーパーではどのようなものを買い、どんな食事をすべきか、などの栄養指導をしています。バレエ選手は体型をキープしつつ、栄養もしっかりと摂取する必要がありますし、特に若い女性選手は貧血や骨粗鬆症などのリスクも高く、注意が必要です。そういったところに配慮しつつ、筋肉をつけながら「食べても太らない体」を選手と一緒に作っていくのが私たちの仕事です。
昔は国内外問わずコンクールなどに帯同していましたが、今はZOOMなどのオンラインで指導できるのが、すごく便利です。授業でも実践的なところを学生に伝えることができ、とても良い環境になりました。

![]()
・・・栄養のスペシャリストである先生が、地域連携に取り組むようになったきっかけを教えてください。
本学では、2019年から子ども食堂の支援に向けた取り組みを実施しており、学生たちが積極的にお手伝いをさせていただいています。そんな中、子ども食堂にトマトを寄付していた若松の響灘菜園さんから「傷みなどで出荷できない規格外トマトを何かに活かせないだろうか」とご相談がありました。調理が難しい場所でも子ども食堂を開き、ひとりで食事する子どもを減らせたら…という思いもあり、2021年に規格外トマトを使用したレトルトカレーのレシピを考案することになりました。そもそも、カレーは給食でも人気のメニューであり、トマトは水分が90%以上あるので、無水カレーにすると栄養価の高い献立となります。


「トマトのおんがえしカレー」開発の様子
プロジェクト発足後、コロナ禍になってしまったため商品化には2年以上かかりましたが、学生にはオンラインでプロジェクトに参加してもらいました。試行錯誤しながらレシピを考案したSDGs商品の「トマトのおんがえしカレー」は2023年に一般販売され、2年経った今でもご好評いただいています。北九州市のふるさと納税の返礼品にも選ばれており、昨年度は北九州市が取り組む「おいしい給食大作戦」という事業で、私たちが考案したトマトカレーを学校給食で調理してもらい、子どもたちに7万食を提供しました。
生産過程においてどうしても出てきてしまう「規格外トマト」は、年間80〜100トンほどあるそうですが、現在私たちのプロジェクトで活用しているのは、せいぜい1〜2トンほどです。今後はシリーズ化して、商品を増やしていきたいと思います。
※産学連携で取り組んでいる「トマトのおんがえしプロジェクト」については、当ブログで「北九州市立高校」の取り組みを紹介しました。
→ブログはこちら
![]()
 「トマトのおんがえしカレー」378円
「トマトのおんがえしカレー」378円
![]()
・・・「トマトのおんがえし」シリーズ商品は井筒屋でも販売し、お客さまにも大変好評です。今年の1月には、新しい商品を学生さんたちに販売していただきました。
「規格外トマト」活用の番外編ということで、門司の敬愛高校さん、イタリア料理店「B&W」さん、佐左井製粉さんとコラボレーションして、一緒に「規格外トマトのマルゲリータピザ」を作りました。ピザソースだけでなく、生地にも「規格外トマト」を入れ込んでいるんですよ!2日間限定の企画でしたが、おかげさまで完売しました。今後も地域のお祭りなどで販売が決定しています。
特に井筒屋さんでは販売もさせていただき、学生たちには「自分たちが作ったものをお客様に買ってもらう喜び」が体験できる、大変貴重な場となっています。

小倉井筒屋での販売の様子
![]() 「規格外トマト」のような、食に関する社会問題の解決に携わることは、管理栄養士の国家資格を取得するための勉強だけでなく、挑戦する力やコミュニケーション能力などを高めることができます。こうした経験を通じて、学生たちには偏差値では計れないもの…例えば自分の価値や得意なことを見つけてくれたら嬉しいですね。実はこの演習が始まってからは企業就職が増えていて、食品メーカーや醤油メーカーに就職した生徒もいます。学生たちの選択肢が増えることは、とても喜ばしいことだと感じています。
「規格外トマト」のような、食に関する社会問題の解決に携わることは、管理栄養士の国家資格を取得するための勉強だけでなく、挑戦する力やコミュニケーション能力などを高めることができます。こうした経験を通じて、学生たちには偏差値では計れないもの…例えば自分の価値や得意なことを見つけてくれたら嬉しいですね。実はこの演習が始まってからは企業就職が増えていて、食品メーカーや醤油メーカーに就職した生徒もいます。学生たちの選択肢が増えることは、とても喜ばしいことだと感じています。
![]()
・・・大学での授業、アスリートの栄養指導、地域連携の取り組みと、3本柱で活躍されている室井先生の、今後の夢や目標をお聞かせください。
今春、大学の地域連携センターの1階にキッチンスタジオを作りました。今後は「地域の食の相談窓口」や「大学生が考える子ども食堂」を展開したいと思っています。いろんな企業の方たちと協力して、食のプロジェクトにも挑戦したいと考えています。また、今後も学生たちと“生きた経験”をしながら、面白いことに取り組みたいと思っています。


![]()
・・・このブログでご登場いただくみなさんにお尋ねしているのですが、室井先生にとっての“サステナブル”とは?そして“サステナブル”の先にあるものとは何だと考えますか?
この質問、すごく悩みますね(笑)。いろいろ考えましたが、サステナブルの先にあるものは「幸せ」かな、と思います。私ももちろんそうですが、スポーツ選手や学生、子どもたちにとって、食生活って生涯健康でいるために大事なことです。「食事の基本を作る」「子どもの味覚を育てる」ことが私達の仕事の一つですが、仕事そのものが、持続可能な取り組みであり、サステナブルと言えるのかなと思います。
今朝も、スポーツ選手に食事指導をしている中で「食事で自分のモチベーションやメンタルが、すごく変わりました。食事を大切にして良かったです」と喜んでもらえたんです。これってとてもサステナブルなことじゃないかなと思いながら…うまくは言えないんですけど(笑)。
![]()
・・・お話をお伺いして、 室井先生の “サステナブル”な行動が、いろんな人やコトを繋げていると感じました。
そうなんです。私も今回の取材を契機に、サステナブルについて思いを巡らせていたのですが、一連の活動を通じて繋がっている皆さんとの関係性は “サステナブル”という共通の思いがあるからこそだと認識しています。そして、家族や子どもとの関係性や距離感においても“サステナブル”というキーワードは本当に大事だと、再確認することができました。
私には小学生の子どもがいて、夕方以降の会議や土日のイベントなどにも子どもを連れて行くことが多くて…。申し訳ないと思うのですが、どの企業の方も嫌な顔をせず、子どもの同伴を快く受け入れてくださり、本当に助かっています。![]()


2024年12月14日に行われた「サンタウォークin到津の森公園」は、九州栄養福祉大学の地域連携授業を受講している学生たちが、連日ミーティングを行い、企業に協賛をお願いするなど一から考えて作り上げたイベントです。当日訪れた多くの参加者は給食ブースでは北九州市の特産品を楽しみ、縁日ブースでは子どもたちの笑顔が弾けるなど、イベントは大成功でした。
![]()
・・・多様性のある働き方は、サステナブルにおける“重要な視点のひとつ”ですね。
子育てと仕事を両立していく中で、理想のワークライフバランスが実現できたらいいなと思うのですが、現実は午後8時くらいに帰宅して午後9時くらいまでにご飯やお風呂を済ませたいから、もう本当にバタバタです(笑)。日曜日くらいは「子どもと一緒に思い切り遊ぼう!」と思いながら、イベントなどの仕事が入ってくると、子どもも一緒に現場に連れて行きます。
私たち親子は旅行が好きなので、私は仕事、子どもは学校を頑張れたら、2人で「パリに行こうね!」という目標を作っています。実現できるように、これからも親子で頑張りたいと思います。
![]()
生き生きと仕事をしている室井先生の姿を見て、お子さんもいろんなことを享受しているのではないでしょうか。豊かな食生活と健康を支える持続可能な社会を目指して、学生たちと一緒に「食」を通じたアプローチで北九州を盛り上げる室井先生の活動を、今後も応援していきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。