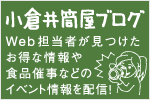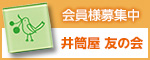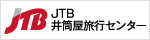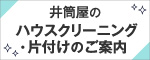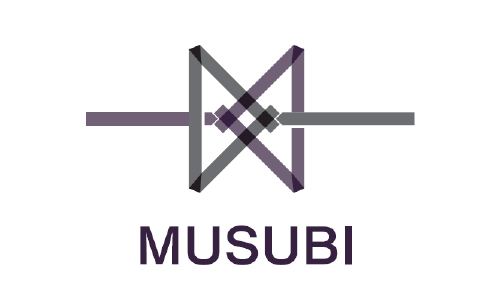
私は新館7階『MUSUBI』に勤務しております終活アドバイザーの宮本と申します。
『終活』に関して「何をしておくべきなのか」、アドバイスや提案を定期的に発信してまいります。ご参考いただければ幸いです。
今回は「法定後見制度」についての話です。

◇法定後見制度とは?
法定後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援・保護するための制度で、本人の判断能力の程度に応じて、「後見、保佐、補助」の3つの分類があります。
◇成年後見人ができること
判断能力がほとんどない人を守る人を「成年後見人」といいますが、成年後見人には法律上、代理権、同意権、取消権などの権限があたえられています。
例えば、判断能力がほとんどない人が必要のない高額な健康食品を購入してしまった場合、成年後見人がそれを返品して代金を返金してもらうことができます。(取消権)
◇成年後見人になれる人
成年後見人になるために特別な資格は必要がなく、成年であればなることができます。最近の傾向として、弁護士事務所や司法書士事務所、NPO法人、社会福祉協議会などが法人として成年後見人を引き受けるケースが全体の8割以上を占めています。
◇法定後見制度を利用するためには
①申し立てのできる人
制度利用の申請は、本人のほかに配偶者、本人の四等親以内の親族です。また、身寄りのない人などは、市区町村長が申立人になることもできます。
②成年後見人の候補者
申立人は成年後見人になってもらいたい人・法人名を記入して申請(申立者が候補者でも可)しますが、守られる人の財産や家族状況により、家庭裁判所が選任した法律や福祉の専門家が成年後見人になることもあります。
③制度利用の手続きと費用
利用するためには家庭裁判所への申立書の提出、家庭裁判所による申立人や本人との面接、「後見・保佐・補助」のどれに該当するかの審判、「東京法務局」への登記等が必要となります。
また、費用については申立費用は申立人が負担。成年後見人の報酬は成年後見人による支払い申立により、1年間ごとの後払いとして報酬を引き出して受け取ります。
今回の話はここまで。次回は成年後見制度の「任意後見制度」について詳しくお話します。
新館7階「MUSUBI(結び)」では、毎週、各種無料相談会を開催しています。ホームページや井筒屋アプリでも相談会スケジュールを発信していますので、空き情報等をお気軽にお尋ねください。
MUSUBI(結び) ホームページはこちら
担当 宮本・吉本・野田
お問い合わせ
■小倉店新館7階 MUSUBI(メモリアル相談)
TEL:093-522-3620
カテゴリー:イベント・キャンペーン
フロア:新館7階